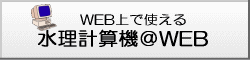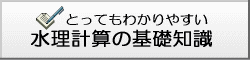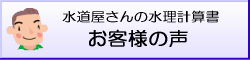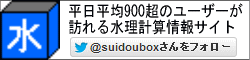水理計算の基礎知識-5章
計画使用水量とは
計画使用水量とは
計画使用水量とは、計算の対象となる給水装置で使用されるであろうと予測される水量のことを言います。
この計画使用水量を基にして管口径や受水槽の容量を決定するため、適切な方法で算出する必要があります。
計画使用水量は「同時使用水量」または「一日当たり使用水量」から求められます。
同時使用水量とは、同時に使用されると予測されるいくつかの末端給水用具から水を流したときに給水装置に流れる水量のことを言い、通常、直結式給水ではこの同時使用水量を計画使用水量として水理計算を行います。
一日当たり使用水量とは、計算の対象となる給水装置で一日に使用されるであろうと予測される水量のことを言い、通常、受水槽式給水ではこの一日当たり使用水量を計画使用水量として受水槽容量を決定し、水理計算を行います。
次章以降で、同時使用水量の算出方法について説明していきます。
同時使用水量の算出方法はひとつではありません。
給水装置の規模や用途に応じて適切な算出方法を用いることで、より実態に近い計算を行うことが出来ます。
計画使用水量の概念をまとめたものが(図5-1)です。
(図5-1)
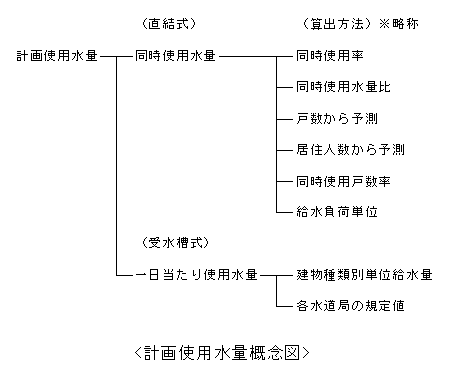
(注意書き)
水道局によっては、建物(給水装置)の種類ごとに算出方法が明確に定められている場合もありますので、事前に水道局あるいは要綱等で確認しておく必要があります。
次へ : 「6. 「同時使用率」から同時使用水量を算出する」
目次へ
前へ : 「4. 納付金と負担金と計画使用水量」