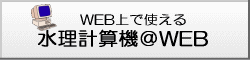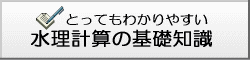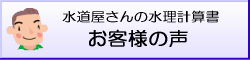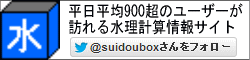水理計算の基礎知識-15章
高さによって失われる力
高さによって失われる力
配水管の水圧が0.147MPaあるとします。
(0.147MPa = 1.5kgf/cm2 = 水頭15m)
この配水管に鉛直線上に上方に向かって管を立てたと仮定すると、この管には水が15m上方まで立ち上がることになります(図15-1)。
(注:この章では「高さによって失われる力」以外の種々のエネルギー損失は考えません。)
(図15-1)
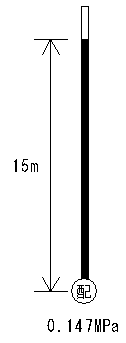
次に、配水管から水平に分岐し、その管を5m立ち上げたケースを考えてみます(図15-2)。
(図15-2)
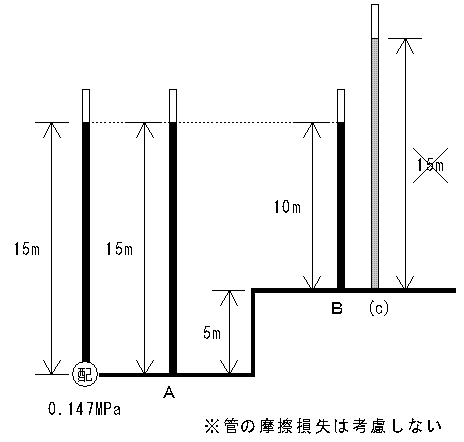
配水管の水圧が0.147MPaですから、A点では水が15m立ち上がります。
B点はA点より5m高い位置にあります。
B点においては既に5m分だけ水を押し上げる力を使ってしまっていますので、水は差し引き10m立ち上がります。
(c)点のようにそこからさらに15m立ち上がるということはありません。
同じ考え方で(図15-3)では、A地点での水頭は15m、B地点での水頭は10m、C地点での水頭は5mとなります。
(図15-3)
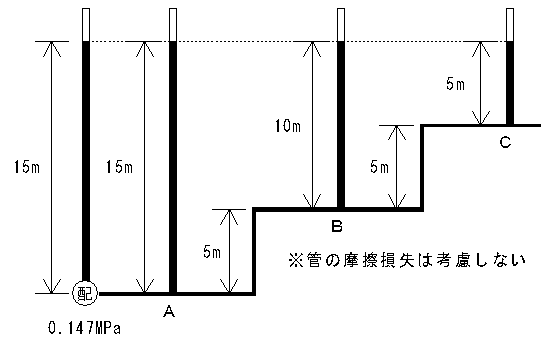
このように、給水管(給水栓)と配水管との高低差を、配水管の水頭から差し引いた残りの水頭が、実際に利用できる水頭ということになります。
この、実際に利用できる水頭のことを、その地点間の有効水頭といいます。
例えば、(図15-3)のA-C間の有効水頭は5mということになります。
(注:管の摩擦損失等がある場合には、それらも差し引いたものが有効水頭となります。)