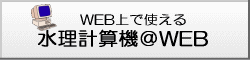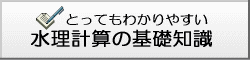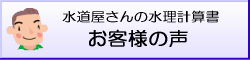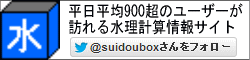水理計算の基礎知識-7章
「同時使用水量比」から同時使用水量を算出する
「同時使用水量比」から同時使用水量を算出する
この算出方法も「同時使用率」から流量を算出する方法と同様、単独給水管のうちさほど規模の大きくない給水装置に適していると考えられます。
「同時使用率」から流量を算出する方法との違いは、流量の偏りを少なくできるという点です。
「同時使用率」から流量を算出する方法では、同時に使用する末端給水用具を任意に設定するため、設定の仕方によっては流量の多い区間が長いケースと短いケースができてしまいます。(図7-1)
(図7-1)
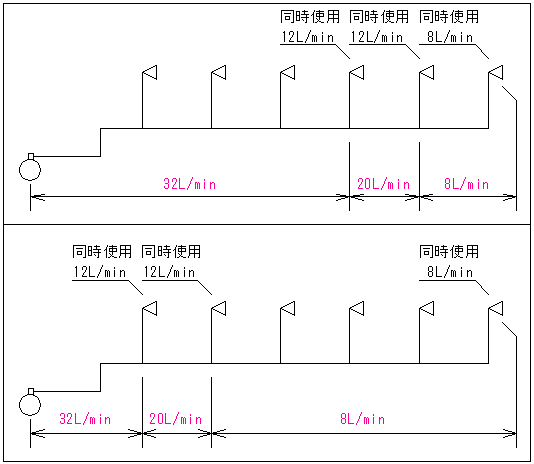
このようなケースでは給水装置全体の同時使用水量は変わりませんが、流量の多い区間の長さが大きく異なるため所要水頭も大きく変わってきます。
任意に同時使用末端給水用具を設定することによって生じるこのような流量の偏りを少なくして、どの区間も受け持つ末端給水用具に応じた流量を設定するのがこの「同時使用水量比」による算出方法であり、「標準化した同時使用水量による算出方法」とも言います。
この算出方法の欠点は、「同時使用率」による算出方法と比べて計算の手間がかかることです。
なお説明の都合上、今後この方法による同時使用水量の算出方法を、「同時使用水量比」から算出する方法、というように表記します。
それでは説明を加えながら、「同時使用水量比」による算出方法で給水装置全体の同時使用水量を算出してみます。
(図7-2)のような給水装置があるとします。
(図7-2)
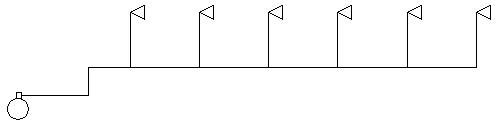
「同時使用率」から算出する方法では、末端給水用具の総数が6栓であることから同時使用末端給水用具数は3栓とし、任意に設定したその3栓分の使用水量のみを「種類別吐水量と対応する末端給水用具の口径」から求めましたが、
■手順1
「同時使用水量比」による算出方法ではすべての末端給水用具の使用水量を「種類別吐水量と対応する末端給水用具の口径」により求めます。
ここでは(図7-3)のように各末端給水用具の使用水量を設定しました。
(図7-3)
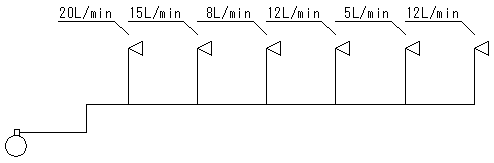
■手順2
そして、すべての使用水量を合算して、末端給水用具の総数で除します。
つまり1栓当たりの平均使用水量を求めることになります。
(図7-3)の例ですと1栓当たりの平均使用水量は、
( 12 + 5 + 12 + 8 + 15 + 20 ) ÷ 6
= 72 ÷ 6
= 12 L/min
となります。
■手順3
次に、末端給水用具の総数に対応した同時使用水量比を求めます。
末端給水用具の総数に対応した同時使用水量比は「末端給水用具数と同時使用水量比」(資料3)により求めます。
(資料3)末端給水用具数と同時使用水量比
| 総末端給水用具数 | 同時使用水量比 |
|---|---|
| 1 | 1.0 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 1.7 |
| 4 | 2.0 |
| 5 | 2.2 |
| 6 | 2.4 |
| 7 | 2.6 |
| 8 | 2.8 |
| 9 | 2.9 |
| 10 | 3.0 |
| 15 | 3.5 |
| 20 | 4.0 |
| 30 | 5.0 |
(図7-3)の例では末端給水用具の総数は6栓ですから、同時使用水量比は2.4となります。
■手順4
最後に、求めた1栓当たりの平均使用水量に、末端給水用具の総数に対応した同時使用水量比を掛けることにより給水装置全体の同時使用水量を求めます。
1栓あたりの平均使用水量は12 L/min、同時使用水量比は2.4でしたから、
12 L/min × 2.4 = 28.8 L/min
というように給水装置全体の同時使用水量を求めます。
まとめますと、
(1) すべての末端給水用具の使用水量の算出
(2) 1栓当たりの平均使用水量の算出
(3) 同時使用水量比の算出
(4) 給水装置全体の同時使用水量の算出
の4つの手順により、「同時使用水量比」から給水装置全体の同時使用水量を算出することができます。
今回の例では一度に給水装置全体の同時使用水量を求めたので、「流量の偏りを少なくする」というメリットと「計算の手間がかかる」というデメリットをあまり感じなかったかもしれません。
次は同じ図の例を用いて区間ごとの流量を算出してみます。
区間は流量が変化するごとに区切り、最下流から計算していきます。(図7-4)
(図7-4)
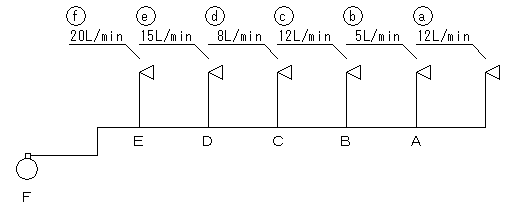
■手順1
a~A間の受け持つ末端給水用具の使用水量を「種類別吐水量と対応する末端給水用具の口径」により求めます。
a~A間の受け持つ末端給水用具の使用水量はaの12L/minとなります。
■手順2
a~A間の受け持つ末端給水用具の1栓当たりの平均使用水量を算出します。
a~A間の受け持つ末端給水用具は1栓ですので平均使用水量は
12L/min ÷ 1 = 12L/min
となります。
■手順3
a~A間の同時使用水量比を算出します。
a~A間の受け持つ末端給水用具は1栓ですので「末端給水用具数と同時使用水量比」より
同時使用水量比は1.0となります。
■手順4
a~A間の流量を算出します。
流量は、1栓当たりの平均使用水量に、同時使用水量比を掛けることにより求めることができますので、
12L/min × 1.0 = 12L/min
となります。
■手順5
以降、同様の手順で上流に向かって計算していきます。
参考としてA~B間とB~C間の流量を手順に従って算出してみます。
(A~B間)
1)A~B間の受け持つ末端給水用具の使用水量
aの12L/minとbの5L/min。
2)1栓当たりの平均使用水量
(12 L/min + 5 L/min ) ÷ 2栓 = 8.5L/min
3)A~B間の同時使用水量比
2栓 → 1.4
4)A~B間の流量
8.5L/min × 1.4 = 11.9L/min
(B~C間)
1)B~C間の受け持つ末端給水用具の使用水量
aの12L/minとbの5L/minとcの12L/min。
2)1栓当たりの平均使用水量
(12 L/min + 5 L/min + 12 L/min ) ÷ 3栓 ≒ 9.7L/min
3)B~C間の同時使用水量比
3栓 → 1.7
4)B~C間の流量
9.7L/min × 1.7 ≒ 16.5L/min
各区間の計算結果を表にまとめたものが(表7-1)です。
(表7-1)
| 区間 | 総流量 (L/min) |
給水栓数 | 1栓当たり流量 (L/min) |
同時使用水量比 | 区間流量 (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| a~A | 12 | 1 | 12 | 1.0 | 12 |
| A~B | 17 | 2 | 8.5 | 1.4 | 11.9 |
| B~C | 29 | 3 | 9.7 | 1.7 | 16.5 |
| C~D | 37 | 4 | 9.3 | 2.0 | 18.6 |
| D~E | 52 | 5 | 10.4 | 2.2 | 22.9 |
| E~F | 72 | 6 | 12 | 2.4 | 28.8 |
以上をまとめますと、
(1) 区間の受け持つ末端給水用具の使用水量の算出。
(2) 区間の受け持つ末端給水用具の1栓当たりの平均使用水量の算出
(3) 区間の同時使用水量比の算出
(4) 区間の流量の算出
(5) 区間ごとに1~4の繰り返し
の5つの手順により、「同時使用水量比」から各区間の流量を算出することができます。
区間ごとに計算をしてみると、「同時使用率」による算出方法に比べて計算に手間がかかるのが実感できたのではないかと思います。
また、区間の流量もその受け持つ末端給水用具に応じてバランスよく算出できるのもご理解いただけたのではないでしょうか。
次へ : 「8. 「戸数」から同時使用水量を算出する」
目次へ
前へ : 「6. 「同時使用率」から同時使用水量を算出する」